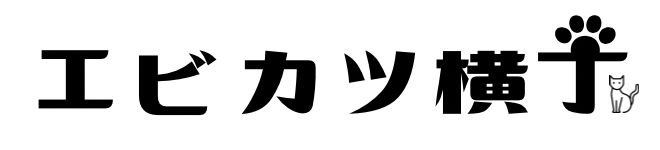この記事では主に研修医や若手医師の方々に向け、医師のキャリアパスについて赤裸々にまとめます。ネタと誇張を過分に含んでおりますので、十分ご理解いただいた上でお読みください。宜しくお願い致します。
医師のキャリアパス
研修医のみんな!これがアナタたちを待つ輝かしいキャリアの選択肢よ!
2024.11 | mermaid での改行を <br> に修正。\n は非対応になったようです(動作確認 v 11.4) Mermaid.js でフローチャートをつくる 仕事の関係でフローチャート的なものを手軽に作る方法[…]
まずは専門医から
臨床医のキャリアについては、若い先生方に何を置いてもお伝えしたいことが1つあります。それは
最低限「専門医」までは取っておこう。特殊キャリア(*)に進まないのなら。
ということです。
今後の人生について特別なプランがなく、最終的に臨床を継続する可能性を捨てないのであれば、何も難しいことはありません。心を無にして専門医までは取る。そこが一旦のゴールです。なぜなら専門医とは「その分野で代替可能な人員として確実にカウントできる」認証マークのようなものだからです。誰かが JIS マークと言っていましたが、言い得て妙です。
専門医は JISマーク
分野にもよりますが、医師6〜8年目までが踏ん張りどころです。最低限ここまで粘って専門医を取っておけば、常勤でもバイト医でも、色々なキャリアを選びやすくなります。
専門医は偉大です。どこの馬の骨ともしれない人も専門医をチラつかるだけで雇用者に「大きな問題なく仕事をこなせる人材」と思ってもらえます。専門医認定は「標準的なことを普通にこなして来た、一定程度ストレス耐性がある人」という証左だからです。
逆に専門医がないと「ペーパードライバーなのでは?」「何か問題がある医師なのでは?」といった疑問を抱かれかねません。認定のため多量のレポートを書く虚無時間や30代での試験対策勉強にはメンタルも削られるでしょうが、心を無にしてやり遂げましょう。
もちろん毒は吐いてもいいです。内科を目指す皆さんは、酒の席で一生 J-OSLERについて愚痴っていいと思います。Osler 先生も皆がベッドサイドに立ち寄らずレポートを書いている姿をみて咽び泣いていることでしょう。ただ今だけは、もうすこし歯を食いしばってください。とにかくまずは「専門医」です。
実は少なくないキャリアの選択肢
はい。本稿で最もお伝えしたい部分は終わりましたが、その先のキャリアについても以下に大別した上で、簡潔にご紹介していきたいと思います。
- 王道(市中病院で臨床を継続)
- アカデミア(大学)
- 開業・地域診療
- 行政・公的機関
- ハイブリ道(企業・海外臨床など)
- フリー道
この記事ではこれらのキャリアパスで求められる適性、メリット、デメリットについて、偏見と勢いだけで述べていきたいと思います。
王道:市中病院コース

初めに紹介するのは「王道」すなわち臨床医としてのキャリアをさらに突き詰めるルートです。
先述したようにまず専門医認定を取った後、その先も基幹病院に残り、臨床部門で指導者になっていくというのがやはり従来型の王道医師キャリアと言えます。
このコースの最終到達点は、急性期病院の診療科部長です。専門医のさらに先「指導医」となり後輩たちを育てるということはまさにJISマークの認証側に回る、ということでもあります。たいへん尊いキャリアパスです。大きな社会貢献です。
求められる適性
このコースに求められる適性は言うまでもなく広い意味での「臨床能力」です。
専門分野に精通し現場で信頼されることはもちろんのこと、コミュニケーション能力、マネジメント力、ストレス耐性、そして自己研鑽を続けるモチベーションが求められます。
メリット:社会保障+安定した給料
このキャリアのメリットは以下の通りです。
- 手堅さ
- サラリーマンであることによる社会保障(保険・年金)
- 昇給の機会が十分にある
- 「教育者」として後輩指導する際の貢献感
- 自己成長の機会が多い
- 中核病院ではモチベーションも維持しやすい
デメリット:多忙・ストレス
問題は、市中病院は(職場にもよるが)一般にずっと多忙であるということです。
- 50を過ぎても休日返上や時間外労働で縛られ続ける状況が持続する可能性。
- 人員が少ない地域では毎日待機かもしれない。
- 高齢者になるまで当直・オンコールをすることになるかもしれない。
- 自律神経の乱れから髪の毛が薄くなるかもしれない。
加えて大病院の部長ともなると、チームマネジメントにも気を使うことになります。コンスタントに研修医から生え抜きを育て続けることには心身ともに一定の緊張感と負担があり続けます。
とくに専攻医たちをバーンアウトさせるわけにはいきません。専攻医は悪くないのです。バーンアウトする医師が出たらそれはあなたの責任なのです。
総括
これらの点から、臨床家として第一線プレイヤーであり続けることにやりがいを感じない人には少々しんどいキャリアパスかもしれません。
コスパを重視するのであれば、このルートを突き進むことなく「専門医認定まで」として区切りをつけるのもまた1つの選択です。一定数が後述の「フリー道」や通称ハイポ病院に流れていくことも自然の成り行きでしょう。
実際、一定規模以上の病院で診療科部長をしている先生方というのはエネルギッシュな人物が多い印象があります。そこまで残っている時点でセレクションがかかっているに違いありません。
アカデミアコース

2つ目のキャリアパスはアカデミア──つまり研究機関たる大学の中でポジションを得ることを目指すルートです。このルートに残り続ける場合は、上記の市中病院王道コースと全く異なる適性が求められます。
求められる適性
基本的にアカデミアは「論文が命」です。ここは臨床家のキャリアではなく研究者のキャリアであり、臨床医としての適性は重視されません。
具体的には、以下をよく理解していることが重要です。
- 英語力は戦闘力
- h-index も戦闘力(*)
- 論文とグラントで人権が決まる
- 論文を書いていないことは働いていないのと同義
- 実はコミュ力(広い意味での政治力)が重要
- いろんな意味で結局コネが大事(国際的にも)
これらを踏まえた上で、泥臭い根気と適度なバランス感、なにより「アウトプットの過程を楽しめる素養」などが求められます。
なおいかに臨床医として現場で信頼される人であっても、その能力は残念ながらアカデミアの人事でほぼ評価対象にならないという問題があります。大学機関にもよるとは思いますが、まずは研究業績の評価を優先するのが一般的な傾向ではないでしょうか。その結果、大学医師はいかに効率的に臨床や教育の時間を減らし研究の時間を生み出すか、というマインドになる傾向があります。こうした環境は診療や教育の質を落とす遠因になっているかもしれません。
メリット:医師としての「深み」が出る
では、医師がアカデミアのキャリアを進むメリットは何があるでしょうか。もちろんキリがないほど無数にあるわけですが、代表的なものを以下に示します。
- 科学の進歩に関われるという夢・ロマン
- 世界中の知識人たちとの議論であふれ出る脳汁
- エビデンス創出に関わっている達成感、やりがい
- 医学博士(PhD)になれる
- 学生・教員アカウントで割引になる商品がある(Macなど)
- 海外を含め旅行(学会)のチャンスが多い
- 海外留学のチャンスにつながりやすい
- 意義不明のペーパーワークで書類処理能力が向上する
- 迷惑メールの処理技術が向上する
- 拒絶(リジェクト)されても折れない心が育つ
- 臨床系教室(大学医局)の場合、さらに以下の特典がつく
- 大学特有の珍しい疾患が診療できる
- ドクタージョイ編集の必要がなく最初から「自己研鑽」になっている
- 給料が出ないので、仕事ではなく趣味なのだと割り切ることができる
- 自宅に帰る必要がなくなる
- 診療に「深み」が出る
デメリット
デメリットについても見てみましょう。私見ですが、アカデミアに進む点について、取り立てて挙げるべきデメリットはないと思います。そんなものあるはずがない。しかし強いて挙げるのであれば、以下の要素があります。
- 無報酬労働が多い
- とにかく給料は上がらない
- ポスドク医員・助教は市中の初期研修医以下の給与所得。
- (ただ他の収入源は確保できるかもしれない)
- 大学院(博士課程)進学が必須
- 博士課程の4年間は当然「学生」になる
- 臨床系教室(大学医局)で学生になる場合、以下の特典がつく。
- 学生なので授業料を払ったうえで大学の臨床業務をさせていただき「勉強」させていただくことになる
- もちろん「勉強」なので給料は(ほぼ)出ない
- その代わり「臨床XX学」の単位が錬成される
- なおこの間、医局費もかかる
- そして学生なので社会保障はない。国保かつ国民年金。
お分かりいただけたでしょうか。
臨床医が大学医局で PhD を取得することは、マイナスからゼロに向かう物語だということですね。でも大丈夫です。博士課程のうちは学割も使えますしiDECOの上限も増えますから自分で資産形成ができます(?)。
それに週2〜3回、外の病院でバイトをすれば給料はある程度維持できるはず。得られるやりがいと「深み」を考えればこの程度の経済的損失は安いものです(?)。
そもそも崇高な医局の中でサイエンスに貢献できるというのにお金?時間? そんなもの気にする必要がありません。我々はここで死に、次の生者に意味を託す。心臓を捧げろ。
ポストない問題
なおこれは医学系教室に限った話ではありませんが、博士号取得後にポストがないというのは本邦のポスドク(PhD取得後の研究者)に共通の問題としてあります。また残念ながら本邦全体のトレンドとしてサイエンス分野での国際的なプレゼンスを落としてきており、研究予算も他国と比べて相対的に少ないといった問題もあります。アカデミア道を本気で突き詰めようという人は海外に出ることも1つの選択肢になるかもしれません。
さらに臨床系教室の場合、科学追及のみならず臨床や医学生教育も担うなど業務量自体が多いという問題もあります。純粋にサイエンスを追及していられるわけでもなく、給与所得は市中病院と比べ格安、それに加え医局運営など政治的側面もあり、基礎医学系や理工系のラボとは一線を画した趣があります。
実際のところ、多くの医師は PhD まで取得した時点でアカデミアを抜け、市中の臨床に戻ります(王道回帰)。ただ結局臨床に戻るだけなのであれば PhD の使い道がなく「足の裏の米粒」(学位を取っても食えないが取らないと気持ち悪い)などと揶揄されがちで、そもそも PhD を取る意味があるのか?という議論も生じています。実際、臨床しかしないのであれば専門医や指導医のほうがPhDより遥かに利用価値の高いものであることは事実です。貴方はどこまでの経済的損失・機会損失を飲み込めるでしょうか。
何かを変えることができる人間がいるとすれば その人は きっと大事なものを捨てることができる人だ
いきなり基礎医学講座へ進むガチ勢ルートも
なお少数派ではありますが医学部卒業後すぐに基礎系教室で(主にwet な)研究にフルコミットするというキャリアもあります。医師というより研究キャリアに集中する道です。その場合は早ければ早いほどよいので、初期研修のみ終えてすぐ(あるいは初期研修もせず直接)その道に進むことが望ましいでしょう。敬意を表します。
当然このコースは臨床の道をほぼ完全に捨てることになりますが、そうは言っても途中から最悪帰ってこられるという意味でやはり non-MD 研究者より「雇用保険」的な意味で恵まれていると思います。
この記事は主に臨床医のキャリアを対象としていますので割愛しますが、有名な中山先生の教室の FAQを読んでその深みを噛み締めて頂ければと思います。
開業・地域密着コース

3つ目のキャリアとしてよく知られるものは開業・地域密着コースです。完全にその土地に根を張ることで、地域住民の支えとして人生を捧げる。
ここではごく一般的なことを述べさせていただきます。
求められる適性
まず開業医の適性として市中病院サラリーマンやアカデミアと大きく違うのは、被雇用者ではなく雇用者・経営者側になるということです。必要な適性としては以下が挙げられるでしょう。
- マネジメント力(スタッフ人事などを含めた総合的な調整力)
- 雇用者・経営者としての手腕
- コミュニケーション力
- マネーリテラシー
- 愛想、人相
全て思うがままにできるという一方、全て自己責任にもなるのがこの道の怖い所です。
メリット
メリットとしては以下が挙げられます。
- 自分の城を築き改善していく達成感
- 仕事のコントロール感(自ら選んだという実感)
- その地域を支えているという実感
- うまくマネジメントすれば得られる収入が破格
これら実感は重要で、仕事のやりがいにも直結するものだと言えます。
デメリット
しかしもちろんデメリットもあります。
- 経営者特有の気苦労
- (一代目の場合)多額の借金から始まる
- (ひとり開業の場合)自分が病気で働けなくなると詰む
- 医業とは全く別の勉強が必要(経営、マネーリテラシー)
なお開業2世以降は箱や顧客ごと引き継げるためこの点で強みがあります。レールを敷かれてここまで歩んできた二世医師たちは窮屈さを感じることも多かったかもしれませんが、経済合理性が極めて高いことは事実でしょう。
行政・公的機関
続いて行政・公的機関です。これまでに紹介したものとは一線を画す特殊キャリアですね。いわゆる医系技官、PMDA、保健所の公衆衛生医師になる道筋がこれです。
求められる適性
- 割と真面目に臨床をやっていたが疲れてしまった
- かといって在宅や地域医療もしっくり来ない
- アカデミアのブラック体質も合わない
……そんな人はこうした特殊キャリアを一度検討してみてもよいかもしれません。
とはいえ筆者はこれらのキャリアに詳しいわけではないためあまり詳細には語れません。ただ医系技官は政治家先生に公衆衛生の政策提案をしたり、大量の印鑑を打ち続けたり、お役所ペーパーを量産したりする気高い仕事だと聞いています。こうした仕事が肌に合うかどうか、適性の問題は確実にあるでしょう。
メリット
メリットは一言で言えば、医師特有のストレスからの解放でしょう。
- 深夜にオンコールで叩き起こされることがない
- 当直で自律神経を乱され寿命を縮めることもない
- シビアな患者さんを受け持って心身をすり減らすこともない
- 論文が形にならず悩み散らすこともない
- 医療訴訟に怯えることもない
- うまく立ち回れば公費で欧米の公衆衛生大学院に留学できるらしい(医系技官)
- 給料もまずまず良い(らしい)
デメリット
注意点として、ホワイトな勤務を期待しすぎてはならない。と聞いたことがあります。
保健所の公衆衛生医師の方から聞いた話では、やはり災害やコロナなど有事のときはかなりの時間外労働になるそうです。まあそうですよね。でもしっかりと時間外を申請できるそうですよ。素晴らしいことです。市中病院やアカデミアと同じですね。やっぱりすごいやドクタージョイ。
またこれも伝聞ですが医系技官は普通にハードワーカーらしいです。実際限界医局員ほどではないでしょうが、そもそも官僚の方々は概してホワイトではないでしょう。夜、霞ヶ関の省庁の窓から漏れる灯りを見てみてください。あの中に医系技官がいます。 そして明日も手裏剣ペーパーを小脇に抱えて議員先生相手にプレゼンテーションだ!
Hybrid 道(なんかスゴい道)
さて、医師免許にはまだまだ他の使い方があります。たとえば製薬やバイオ企業に就職したり、海外の臨床や公衆衛生の現場で働いたり、いきなり起業してみたり、とにかくグローバルなハイブリ道──通称「なんかスゴい道」です。医師免許というある種の雇用保険を手にアドベンチャーするのです。
急に語彙を失ってしまったのは言うまでもありません。普通の臨床キャリアを歩んできた筆者とは縁遠い話すぎてあまりにも情報がないのです。ただこれだけは言わせて下さい。「私は敬意を表する」
フリー道
一方ここまで述べたような道を進まずにぬるっとバイト医として生きることも可能です。通称ゆるキャリです。
とくに専門医認定さえあれば、仕事の選択肢は無数にあります。交渉次第で週1〜3外来のみ勤務などの就労環境を手にする事は十分可能でしょう。産業医であればさらに可能性は広がりますし、他にも訪問診療といった選択肢があります。通称ハイポ病院の医局で枯れた植物になることも可能です。
専門医取得以降はもう「頑張らなくてもいい」のです。専門医という時点で十分それまで頑張ってきているわけですから。その先は仕事を選びながら、バランスの取れた生活を謳歌して良いと思います。医師業をフレキシブルに行いながら、子育てや趣味にフルコミットする選択肢も十分にあるでしょう。慌てる必要はありません。
m3.com、民間医局、なんでもいいです。いま皆さんが現場で揉まれすぎて疲れてきているなら、医師求人を見てみてください。きっと気持ちが強くなるはずです。多少休んだところで大きな問題はありません。疲れたなら休めばいいのです。
おわりに:キャリアの先の人生

ニッポンは斜陽とはいえ、恵まれた国です。ご飯は美味しいし、普通に生きていれば住む場所にも困らない。トイレは清潔で治安もいい。電車で隣に座ったアンちゃんがバッグの中に銃を忍ばせている可能性はほぼ0だし、黄色人種だからという理由でいきなり殴りつけられることもない。国民の多くは穏やかで勤勉で、和を大事にする。こと生活という観点において文句のつけようのない環境です。欠点をあげるとすれば、少子高齢化で今後経済的に厳しいシナリオが濃厚である点くらいです。しかしそれでも多くの他国と比べれば十分に恵まれています。
その中にあって医師国家試験に合格し、臨床研修も終え、専門医認定まで生き残ることができたのであれば「人生の基盤を作る」という意味では正直ゴールです。適切なマネーリテラシーを持って仕事を継続すれば十分な生活水準を維持できるでしょう。
以前、ある医師は言いました。
専門医取ったし結婚して子供もできたし、自分の人生はもう消化試合ですわ。もう子供の将来に投資するくらいしかやることないわ。
大変印象的な言葉です。そしてなにより「深み」がある。ある程度やることをやってきたからこそ得られる、自己肯定感を伴う緩やかなバーンアウト。「もう十分頑張ったよ自分」という思いが喉をついて吐露されたかのような。
そこまでいったら、休んでいい。私もそう思います。だからこそ研修医の先生方におかれてはまず「そこ」まで辿り着くことを目標にしてほしいと思います。仕事の選択肢が増えることはきっと貴方の人生にとってプラスになるはずです。
まとめ
- 専門医を取ろう。それからは少し休んでもいい。
- その先の人生に何かやりがいを見つけようと思ったら、キャリアの選択肢は実はたくさんある。
どのキャリアを選んでもいいのです。私たちは自由なのですから。